社外取締役対談「中長期ビジョンの実現する取締役会の実効性とは」
大塚がトータルヘルスケア企業として持続的に成長するため、取締役会の実効性をどう高めていけばよいのか。企業での勤務経験の豊富なお二人に、議論していただきました。

詳細はこちら
新経営体制における取締役会に期待すること
青木取締役 取締役会において最も重要なことは、社内外に関わらず取締役一人ひとりが活発に意見を言い、十分な議論を行ったうえで最終的な結論を引き出す事が本当の実効性を担保することだと思っております。井上社長は、意見をしやすい雰囲気をつくることに長け、議論に耳を傾けたうえで決断するタイプであると思います。今までもそうですが、取締役会は形式的な審議で終わることなく意思決定がなされてきており、今後も、井上社長ならではの運営で取締役会のさらなる活性化が図られていくと思います。
三田取締役 私は社外取締役に就任して5年目になりますが、当初から取締役会での議論は活発で、特に社外取締役が多様な視点から意見を述べる機会が豊富にありました。事前の説明も丁寧で、担当者の方々が私たち社外取締役も十分な理解が得られるように資料の準備や説明に時間をかけてくださっています。事前のサポートがあることで、議題に対する理解が深まり、取締役会当日には多くの観点から建設的な質問を投げかけることが可能になります。その結果、社内で十分議論しつくされたものであっても、取締役会で「時期尚早」との意見が出て、議案にブレーキがかかることがありました。これは取締役会の実効性が発揮されていることの表れです。今後も、体制を含めたグループ全体のあり方について、時代の変化に合わせて議論を深めていくことが重要になってくると考えます。
青木取締役 商社出身の私は、M&Aや事業構造の経営的な視点から、三田取締役は証券会社のアナリストとしての知見から、他の社外取締役は医療や会計などの専門的な立場からそれぞれ多角的な視座を提供していますので、取締役会はいい緊張感が生まれています。また取締役の多様性については形式的に対応するのではなく、例えば外国籍の取締役については先ずは大塚製薬で3人の外国籍の取締役を登用し、その実効性を確認しながら、どの様な形で大塚ホールディングスの役員構成にすべきかを考えています。形式的な対応ではなく、実際に効果を発揮するかどうかを丁寧に見極めた上で対応を決めている点が、大塚の良さです。「実」を大事にする会社だと感じています。
三田取締役 大塚ホールディングスでは第4次中計において取り組む社会課題の一つとして「女性の健康」を掲げており、NC関連事業などヘルスケアの事業において女性の視点が重要だと考えています。このような事業環境の中、取締役会に女性は私以外に、牧野取締役CFO、東條取締役、大澤監査役、辻監査役がいますし、グループの子会社でも多くの女性の経営幹部が活躍されており、女性の登用はかなり進んでいると言えます。女性の健康という社会課題に取り組む事例として、日本では専門医や自治体と連携し、一般の方への啓発活動だけでなく企業への疾患セミナーなどを通じて、女性の健康課題を社会全体で支援できるように様々な取り組みを行っています。米国では、日本でブランド価値を確立させたエクオール含有食品「エクエル」の展開、ユコラ社、ボナファイドヘルス社の買収等を行っています。また、大塚ホールディングスは第4次中期経営計画で「女性の健康への貢献度」をマテリアリティの指標として掲げています。

イノベーションを加速する人的資本と財務戦略
三田取締役 グローバルの人財育成の仕組みが作られつつありますし、グループ各社間の人財交流も進んでいる印象を受けています。大塚ホールディングスの経営企画部や財務会計部には、複数の子会社から出向や兼務の形で多様な人財が集まり、グループ全体を俯瞰する視点を養う機会が広がっています。こうした人財が事業会社へ戻ることで、ホールディングスの視点が各社に浸透しますし、社員同士の相互理解が深まり、コラボレーションやタスクフォース型プロジェクトの基盤が築かれていると感じています。実際、ある事業会社が医薬品の開発を始めた際、開発ノウハウがある別の事業会社と連携し、横断的なプロジェクトチームがつくられました。このような取り組みは、人財の流動性の向上にとどまらず、事業そのものの進化を後押ししています。人的資本を戦略的に活用することで、イノベーションの創出と企業価値の向上につなげていると感じています。
青木取締役 大塚の社員は、創業の精神である「大塚にしかできないこと」を実践していますが、それを続けることこそが大きな強みです。ポカリスエットやカロリーメイトは、製品価値に対する理解浸透にいくつものハードルが当初ありましたが、大塚のポリシーを貫き、粘り強く育てたからこそ、これほどまでにマーケットに受け入れられたのでしょう。時間をかけて企業としての存在意義を示す取り組みは、強い目的意識と大塚の財務基盤が強固であるからこそと言えます。
三田取締役 近年、大塚の財務戦略は目に見えて変化があると感じています。その中でROIC経営の導入・浸透は顕著で、ホールディングスだけでなく、子会社単位でもROICの考え方に基づいた経営判断が行われるようになっています。現在では、製品や事業単位での損益管理が進み、自らの収益構造をより深く理解し、戦略的に資源配分を見直すようになっています。また財務基盤が充実しており、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を活用することで、子会社はグループ内で資金を効率的に融通でき、迅速な投資判断が可能になっています。こうした変化は成長領域への投資強化だけでなく、見直すべき事業の選別も進み、グループ全体の成長につながっていくと思います。

トータルヘルスケア企業としての中長期ビジョン
青木取締役 大塚がトータルヘルスケア企業として持続的に成長するには、長期経営戦略を構想し、今後の経営環境の変化に機敏に対応できる体制整備が不可欠だと思っています。第4次中計はこれまでの成果を土台に、次のステップへ発展させるための準備段階にあると捉えています。経営を取り巻く環境はますます複雑化し、個の力だけでは対応しきれない局面が増えてきており、大塚グループがさらに拡大するには、グループ全体で将来のあり方を見据えた議論が必要です。水面下ではその準備がしっかりと進んでいることを実感しています。
三田取締役 第4次中期経営計画は、5年間という限られた期間ではありますが、この先長く続く企業の歴史の中では、重要な期間の一つとの位置づけです。計画策定にあたっては、第5次中計以降を見据えた議論が重ねられており、今はその基盤を築く「仕込み」の時期だと捉えています。医療関連事業のフェーズ2以前の開発品は、第5次中計以降で花開くものと期待できます。幸いにも業績・財務基盤ともに良好な状況にあり、2024年度はジュナナ社の買収、大塚製薬工場の米国進出や、2023年度から取り組んでいるポカリスエットの米国展開など、将来を見据えた積極的な投資が進みました。成果が目に見える形となるには一定の時間を要するかもしれませんが、中長期的な視点でグループの進むべき方向を見極め、建設的な議論に貢献していきたいと考えています。
社外取締役対談「指名・報酬委員会での議論と新CEOに期待すること」
2025年1月に井上新CEOが就任したことを受け、指名・報酬委員のお二人には、その選任の過程や、大塚の企業価値向上のための取締役会のあり方について語っていただきました。

詳細はこちら
後継者選任の過程
松谷取締役 大塚ホールディングスは2023年4月より、コーポレートガバナンス委員会の小委員会として指名・報酬委員会を設置しました。指名・報酬委員会は、これまでコーポレートガバナンス委員会で審議されてきた社長その他経営幹部のサクセッションプランなどについて、より具体的に検討を進める組織で、総務担当取締役およびすべての社外取締役で構成されています。指名・報酬委員会の設置は、今まで以上に自律的で透明性の高い企業経営を行う重要な一歩だったと感じています。新CEOの具体的な候補者検討にあたり、私は2桁の候補者と面談を重ね、研究・営業・企画・経理など幅広いバックグラウンドを持つ方や、キャリア採用の方も候補に挙がっており、大塚には多様な人財がいることを実感しました。
北地取締役 2017年に独立行政法人経済産業研究所(RIETI)のコーポレート・ガバナンス・プロジェクトの成果として刊行された『企業統治と成長戦略』によれば、3人以上の独立社外取締役による監督機能強化とガバナンスに強い関心を持つ機関投資家との対話によって規律付けが強くなるとも指摘されています。当社の指名・報酬委員会は社外取締役が5人いますから、ガバナンスの実効性という点で意義深い取り組みと言えます。
大塚グループは、現場で育まれた人たちが集まる組織で、「ミーイズム(私)」より「アワーイズム(私たち)」を重んじる文化が根付いています。井上社長は、医薬だけでなく複数の事業でのご経験から現場をよく理解し、アワーイズムを体現している方であり、リーダーにふさわしいと素直に納得しました。

次代を見据えたリーダーシップへの期待とガバナンスの進化
松谷取締役 井上社長はCEOとして求められる決断力、これまでの豊富な経験を活かした医療関連事業やNC関連事業のすべてのバリューチェーンを理解してマネジメントする能力、また、社内外とのネットワークを構築できる人間力を有し、ますます重要になるグローバル感覚に対しても積極的に学び続ける意欲を感じているので、リーダーとしてさらなる成長をとげられることを期待しています。
北地取締役 私は、資本市場の変化に機敏に対応する力はCEOに不可欠な資質だと考えており、井上社長がファイナンスの状況や投資家のニーズを敏感に捉え、経営に反映する感度を一層高めていくことを期待しています。大塚グループは医薬から人々の健康を維持向上するヘルスケア、物質化学の基盤も担うプラットフォーム企業として様々な競争とイノベーションが必要ですが、その経営にはartisticな技能・度量が強く影響すると思います。STEMではなくSTEAM*という表現もされますが、人の健康や生命に関わる大塚のような企業においては、合理性だけでなく、Artsの要素が重要です。その点、井上社長は柔軟な感性と見切りの経験を重ねており、CEOの立場としてグループをより発展させていくことを確信しています。
* STEAM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, and Arts
松谷取締役 私は医師として、医療現場でも「Arts and Science」が重視されていることを感じています。患者に寄り添う中で得られるひらめきや直感は、重要な力です。井上社長は穏やかな雰囲気とは裏腹に、必要な場面では厳しい決断を下す覚悟と胆力を備えた方です。実際、取締役会での振る舞いや運営からも、そのバランス感覚と意思の強さが伝わってきます。
北地取締役 そうした資質を備えたリーダーのもとで、取締役会や指名・報酬委員会も、より高いレベルでの運営が求められていきます。インベストメントバンカー出身の瀬口二郎氏が新たに社外取締役に加わったこともあり、取締役会に新たな刺激と緊張感が生まれています。委員一同、強い使命感を持ってガバナンスのさらなる高度化に取り組みます。
サステナビリティ経営を支える報酬制度のあり方
松谷取締役 報酬制度の変更は、大塚の企業価値向上における進化の一環と捉えています。固定報酬中心だった体系から、中長期的な成果を重視する変動報酬へと段階的に移行し、さらに近年では、社会的要請を踏まえて非財務指標の導入も進めました。例えば、ESG関連の外部評価指標であるFTSEのスコアを、株式報酬制度に組み込み、客観的な評価軸を設定しています。透明性の高い判断を行うことは、社内外に対して大塚の姿勢を明確に示す意味でも重要であり、着実に制度改革が進んでいます。
北地取締役 ESGスコアの反映は、報酬制度そのものの質的な進化を象徴する取り組みです。サステナビリティ経営にも取り組んでいるからこそ報酬制度への導入が可能になったのであり、仮に達成が難しかった場合でも、基準を緩めるという発想は一切ありません。大塚グループはサステナビリティ経営のもと、社会、顧客、従業員、株主、ビジネスパートナーといったすべてのステークホルダーに対して、持続的にリターンをもたらすことを使命としています。報酬制度においても、長期的な視点での企業価値向上を支える仕組みづくりを進めていきます。

新任社外取締役メッセージ
インベストメントバンカーとしての豊富な知見を価値創造に活かす
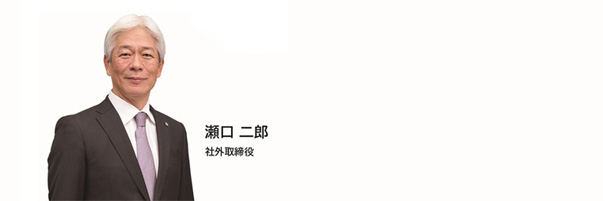
詳細はこちら
私は、東京銀行(現 三菱UFJ銀行)とメリルリンチ日本証券(現 BofA証券)にて、インベストメントバンカーとして資本市場を通じた企業支援とガバナンス強化に取り組んできました。今回、上場企業の社外取締役を初めて務めるにあたり、これまで培ってきた経験を最大限に生かし、大塚ホールディングスの中長期的な成長に貢献していきます。
大塚グループとは、私がメリルリンチ日本証券に在籍していた2009年に徳島の工場を訪問して以来、ご縁が続いています。資本市場との対話やアドバイザリー業務を通じ、大塚グループのトータルヘルスケアへの真摯な取り組みや、挑戦を続ける企業姿勢を直に感じることができました。また、ヘルスケアへの貢献という目指す姿を一貫して持ちつつ、新たな成長分野へ挑戦していることにも共感を深めてきました。
その後、再び徳島を訪れる機会があった際に、地域の方々と会話する中で、大塚グループが地域に根差し、地域社会に貢献していることを知りました。100年以上企業が存続できる理由とも言えると思います。
私は、バブル崩壊、金融危機、リーマンショックといった激動の時代を企業経営の最前線で経験してきました。短期的な成果を追うのではなく、環境が目まぐるしく変化していく中でも長期にわたる信頼関係の構築こそが、企業の発展には必須であると確信しています。この考え方は、健康維持・増進や未病対策などの社会課題解決に取り組み続ける大塚グループの姿勢にも通じるものです。
今後は、大塚ホールディングスの社外取締役として、外部の視点から資本市場の期待に応える透明性の高いガバナンスを支援し、大塚グループの収益性や資本効率の改善に目を配りながら、取締役会で建設的な議論を重ね企業価値の持続的な向上に寄与していきたいと思います。









